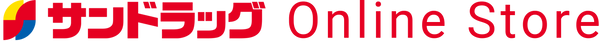☆時間栄養学~パート1~☆
◆体内時計とは?
◆体内時計がズレてしまうのはなぜ?
【サンサイクル栄養士・管理栄養士考案おすすめレシピ】
◆かぼちゃのココット
普段あまり意識しませんが、私たちの体は地球の動きに合わせて約24時間周期で動いています。

ぴったり24時間で動いているわけではないので、体内のリズムを刻んでいる「体内時計」のズレが少しずつ生じていきます。
数分、数時間のズレではたいして体に影響はないかもしれません。
今後、体内時計の管理を行っていくことがとても大切です。体内時計をじっくり検討したことはいろいろあります。
・時間薬学
・時間医学
・時間生物学
・時間栄養学
・時間運動学
ここでは「時間栄養学」について見ていきます。
◆時間栄養学とは?
1日のリズムの中で、
①食べる時間によって、栄養の効果が違う
②栄養素や食品の成分によって体内時計が変化する
ことを考慮し、「いつ何をどれだけ、どれを食べたら良いのか」ということを考えた栄養学のことです。
時間栄養学を考えるために重要になってくるのが「体内時計」です。体にあるといわれる「時計遺伝子」がリズムを刻んで、1日およそ24時間の周期で変化させています。食事の時間になるとお腹が空きますよね?
この「時計」がズレてしまうと体の様々な仕事がうまくいかなくなったり、肥満、糖尿病などの代謝異常、さらにはガン等の免疫疾患の発症に関わるとも言われています。
「体内時計」を考えて食事をすることで・・・
・栄養素を効果的に補うことが出来ます。≪ ~時間栄養学~パート2 ≫
・どうしても夜型の生活になってしまう方の対策も出来ます。
今回は「体内時計」がどのように影響するのかを見ていきます。
◆体内時計がズレてしまう原因
・ヒトの体内時計は24.5時間と元々少し長い
・起床時間や食事の時間が不規則
・光の影響
◆では、このズレを解消するには?
①「時計遺伝子」に刺激を与える。
時計遺伝子は地球上の動植物に存在しており、地球の自転周期にほぼ一致した24時間周期のリズムを持っている主(親)時計と末梢(子)時計があります。
★主(親)時計・・・脳に存在します。夜間に増加し、ズレをリセットしないと脂肪やコレステロール合成などが促進されてしまいます。
★末梢(子)時計・・・内臓や細胞など様々な組織に存在します。糖質・脂質・エネルギーの代謝を促進します。
この2つのそれぞれをリセットしてあげることが大切です。
また、主(親)時計にだけ刺激を与えて体に命令を出しても、末梢(子)時計はまだ動いていないのでエネルギー産生などを行う準備が出来ていません。
この2つのどちらもリセットしてあげる必要があります。

②「体内時計」を遅らせない
・夜に浴びる光
体内時計を遅くすることがわかっています。 特にパソコンやスマホのブルーライトのような青色の光は体内時計を2時間程度遅らせるといわれていますので、寝る前にはできるだけ見ないようにしましょう。
・飽和脂肪酸が多い高脂肪食、カフェイン
体内時計を乱してしまいます。摂り過ぎに注意しましょう。
飽和脂肪酸が多いもの 例)スナック菓子、ケーキなどの洋菓子
カフェインを含むもの 例)コーヒー、紅茶、緑茶など
◆リセット方法
・主(親)時計をリセットする・・・朝日を浴びる
起きたらカーテンを開け、太陽の光を浴びるようにしましょう。
・末梢(子)時計をリセットする・・・朝食を食べる
朝起きてから2時間以内に食べることが重要です!それより時間が経ってしまうと体内時計はリセットされにくくなります。 糖質+たんぱく質を摂ることで、体内時計は一番大きく動きます。
例)ごはん+焼き魚
そんなことで良いのか~と思われた方も多いかもしれませんが、これで朝食の重要さがより分かりましたね!
時間のない朝も、しっかり食べてから頑張りましょう!